こんにちは。フルタ(@Furuta_Jamaica)です。
ジャマイカで一年生の算数を教えていて、意外と難しいなぁと感じることがあります。
それは
「10+いくつ」
の計算です。
例えば、10+3とか10+5とか。
これ、僕たち大人からするとめちゃめちゃ簡単な計算ですよね。
10に3くっつけて13という考えなくてもわかる問題。
ただ、ジャマイカではこれがあまりうまく定着しません。
この指導を色々考えていたら、面白いところが見えてきたのでまとめてみようと思います!
繰り上がりの前に大切な10+〇
10+3の形の計算は、繰り上がりの足し算を教える前にできるようになっておかなければいけない大切な内容です。

アメの個数を10個のまとまりを作って数えようというような活動をして導入してみました。
10+3を数え足しする子どもたち
そのあとドリルを使って10+いくつの練習をしました。ただ、ここで少し気がかりなことが。
多くの生徒が10+3でも数え足しをし始めた。

以前まとめたオールマイティ型の方法で。

こんな感じ。
10+いくつならすぐに答えが見える、という理由で10のまとまりを作る計算を目指してやって来たのに、結局数え足ししてるんじゃあ意味ないじゃないか。
こりゃあ少し工夫が必要そうです。
もっと視覚的に理解させよう
たとえば15は10と5がくっついてるよということを感じてもらうために、こんな紙を使ってイメージ作り。
10と5がくっつくと

15になるよ。


子どもたちこの動作がキスしてるように見えるとか言って大興奮でした。笑

それでも数えちゃう
これを何回も何回も繰り返して、数字を見なくても言える状態になってきました。
そうなったら今度は繰り上がりの練習のための、具体物を見て10+〇を考える練習です。
10と8。

それぞれの大きさは一瞬で特定できるようなトレーニングを積んできました。
しかし、、、、やっぱりまださっきの数字とこの量がつながっていないからなのか、この図になっちゃうと一から数え始めちゃう子がちらほら。

これはドリルをやっている子の写真なんですが、一個一個数えちゃってますよね。
数字を見ながら10と9で19というのは言える。
図を見ながら、それぞれは10個と9個だというのもわかる。
でも10個と9個で?と言われると一番目の丸から数えちゃうんですね。
「1,2,3・・・19」と。
これは何なのか、数える癖がついちゃっているのか、それとも量で考えることに慣れていないからなのか・・・。
これも図→数字→図→・・・の繰り返しで定着するまで何度もやるしかないかな。
言語の違いからくる定着の差
この一連の内容を指導していて、ひーしひしと感じさせられたのが言語の違い。
算数の理解と言語がこれほど関係しているなんて思いもしなかったので、すごく面白く感じました。
数字に適した日本語
日本であれば13は「じゅう・さん」と呼ぶわけです。だから10と3で13ということが理解しやすい。
もっと大きくなって例えば38とかになっても「さん・じゅう・はち」となって今度はかけ算の要素が入ることで、十がいくつ分かということも簡単にわかるようになっている。
つまり日本語は位取り記数法に基づいた数の読み方をしているということなんですね。
あぁ、日本に生まれて良かったー!
英語だと少しややこしい
それに比べて13は10と3でも「テン・スリー」とは言いません。
「サーティーン」という別の言い方に変換しなくちゃいけないんです。
これもダースの文化から来てたりするのかな。
これがもし「テン・スリー」という読み方で統一されていたりしたら、今日書いている内容を教えるのはそこまで難しくないと思います。
ジャマイカでは位取りの理解度の低さが致命的ですが、それはこういった位取りの考えと一致していない数の呼び方をすることからも来ていると思います。
いままで日本の言葉と算数の理解をつなげて考えたことなんてありませんでしたが、こうやって海外に来て違うものに触れることで、気付いていなかった良さや仕組みを考えられることがとても楽しい!!
フランス語はもっとひどかった
そんなこんなで他の言語はどうなんだろうなぁ~と思って、調べているとどうやらフランス語がヤバい。笑
ざっと調べただけでもこんな感じ
- 数字に男性形と女性形がある
- 16まで不規則な形
- 70台は60+〇という表し方をする
- 80台は4×20という表し方
- 90台は4×20+10
なんじゃそりゃ・・・。
96とかだったら「4×20+16」という表し方をするということ。
なんか、もうその言語を使ってる時点で結構キツイ気がする。笑
まとめ
日本では簡単に思える10+〇という計算。
ジャマイカで教えていく上では、言葉の違いを理解したうえで、日本での指導よりもより丁寧に工夫してやらなきゃいけないことわかりました!
算数教育っておもしろい。

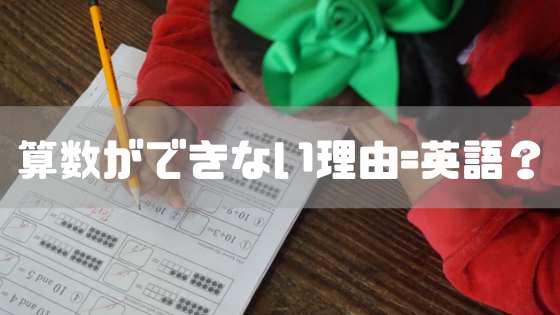



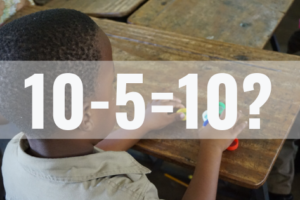
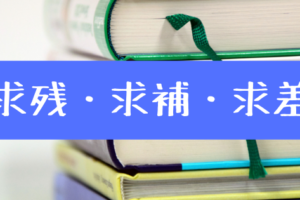

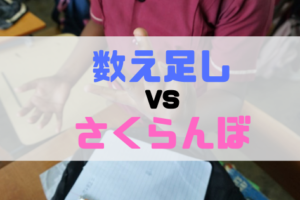

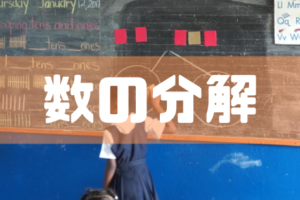




スペイン語と日本語は同じアルファベット読みで似ているー覚えやすいと言われていますが、数字の数え方も16以上は日本語と同じように位取りになっていますね〜
もうずいぶん前の記事のようですが、出会ってしまったので、コメントさせてもらいます。
とても興味深いお話ですね!日本語の表記って、わかりやすいようになっていたのですね。違いを知ることで自らの発見がありますね。
謎の引き算も読ませていただきました。ひく数を足してまた引いて、答えはひかれる数といつも同じという…
小2息子の母親です。1年生のときに不登校になりましたので、勉強をすべて私が教えることになりました。そこでわかったのが、概念のない子にモノを教えることの難しさ、奥深さです。
息子はそれまで算数のテストの点はとれていたので、できる方なんだと思っていました。しかし、自分で教えるようになって気づいたのが「算数の文章問題の意味がわかっていない」ということでした。理解して足す・引くを判断しているわけではなく、ただ、「たしざんの単元だから」たす、「ひきざんの単元だから」ひく、ということでした。ランダムに文章題が出るとお手上げ。さらに、数の概念もよくわかっていないようでした。
そこからは理解してもらうため、具体物や手作り教材での説明、工夫に工夫を重ね、なんとか平均の学力までこれました。
先生たち、ホントに頭の下がる思いです。